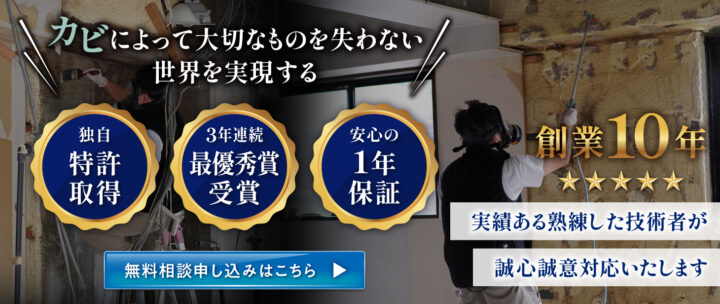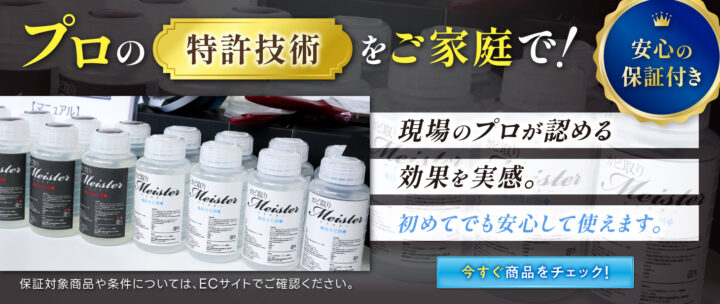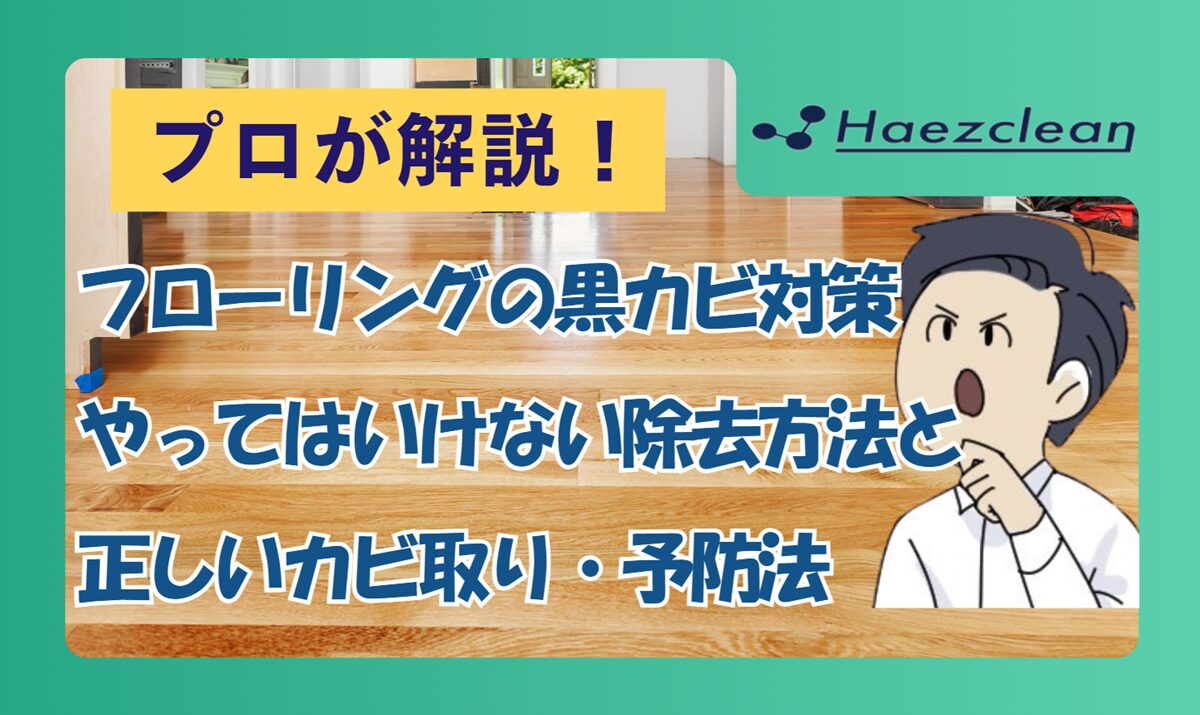

「布団を敷きっぱなしにしていたら、フローリングに黒いシミが……」
「雑巾で拭いても、全然黒カビが落ちない。自力で除去することはできないの?」
同じ場所に家具を置きっぱなしにしたり、カーペットや布団を敷いたままにしていると、久しぶりに動かした際にフローリングに黒カビが発生していたというケースは少なくありません。
黒カビは木材の奥深くまで根(菌糸)を伸ばすため、放置するとフローリングの腐朽や変色が進み、高額な除去費用やリフォーム費用が発生する恐れがあります。
さらに、カビが発生している部屋では空気中に大量の胞子が舞い、アレルギーや気管支ぜんそくなどの健康被害につながるリスクも高まります。
だからこそ、黒カビを見つけたら早急に、かつ正しい手順で対応することが重要です。
本記事では、フローリングに発生した黒カビの除去方法、やってはいけないNG対処法、再発を防ぐための予防策までをプロの視点で詳しく解説します。
青カビや白カビなどの対処方法についても触れていますので、フローリングのカビでお困りの方は、ぜひ最後までご覧ください。
| この記事でわかること |
|
目次
1. フローリングに黒カビ発生!?どんなリスクがある?

フローリングに発生する黒カビは、見た目の問題にとどまらず、健康被害や床材の劣化、さらには住宅の資産価値の低下にもつながる厄介な存在です。
「少し汚れているだけ」と油断して放置していると、気づかないうちに被害が広がってしまうこともあります。
ここでは、黒カビがもたらす代表的な3つのリスクについて、詳しく解説していきます。
1-1. 黒カビが引き起こす健康リスクとは?
黒カビの胞子は2〜4μmと非常に小さく、空気中に浮遊しているため、呼吸とともに体内に入り込みやすいのが特徴です。
吸い込むことで気管支ぜんそく、過敏性肺炎、アレルギー性鼻炎、皮膚炎など、さまざまな健康被害を引き起こす可能性があります。
特に注意が必要なのは、免疫力の低い小さなお子様や高齢者、ペットのいる家庭です。
症状に気づかず放置すると、慢性的な不調につながることもあります。
また、カビの種類によってはマイコトキシン(カビ毒)を発生させるものもあり、頭痛や倦怠感などの原因になるケースも報告されています。
1-2. 放置すれば床が崩れる!?建材へのダメージ

黒カビの恐ろしさは、見た目だけではありません。
木材の内部まで根を深く伸ばして侵食するため、表面を拭いても根本的な解決にはならず、何度も再発を繰り返す原因となります。
初期段階ではシミやざらつきなどの変化にとどまりますが、進行すると床がブカブカする、軋む、波打つなどの物理的な異常が現れます。
さらに悪化すると、合板や根太(床の土台)にまでカビが入り込み、張り替えが必要になることもあります。
被害が表面だけで収まっていれば簡単な補修で済みますが、内部まで達すると工事規模が大きくなり、費用も跳ね上がります。
1-3. 住宅の資産価値も下がる?見過ごせない経済的損失
黒カビによる腐敗は、単なる見た目の問題にとどまらず、住宅全体の資産価値を下げる重大な要因になります。
不動産の売却や賃貸の際にも、「床にカビがあった」というだけで価格交渉の材料やトラブルの火種になることも少なくありません。
特に、黒カビが根太まで侵食している場合は、床の全面張り替えや下地の補修が必要になり、数十万円規模のリフォーム費用が発生する可能性もあります。
一方で、初期段階で気づいて対処できれば、簡単な作業や低コストで済むことがほとんどです。
被害が深刻化する前に対応することが、健康面にも経済面にも最も効果的な対策となります。
カビ汚染度調査・ガス滅菌・カビ取りをご検討の方はこちらからお問い合わせください。
2. カビ取り前に要確認!やってはいけないカビ対処法

黒カビは放置するとどんどん広がっていき、健康被害やフローリングの劣化を引き起こします。
しかし、除去のやり方を間違えると、かえって被害を拡大させたり再発しやすくなることもあります。
ここでは、ついやってしまいがちな「NGな除去方法」を解説します。
失敗を防ぐために、事前にしっかり確認しておきましょう。
2-1. 掃除機で吸い取る

カビをゴミやホコリと同じように掃除機で吸い取るのは厳禁です。
カビの胞子は2〜4µmと非常に小さく、家庭用掃除機のフィルターを通過して排気とともに拡散してしまいます。
これにより、床だけでなく壁や家具、カーテンなど周囲に再付着し、被害が一気に広がるおそれがあります。
掃除機でカビを吸い取るのではなく、必ず殺菌効果のある液剤で拭き取るようにしましょう。
2-2. 塩素系カビ取り剤を使用する

浴室用の塩素系カビ取り剤(例:カビキラーなど)は、たしかに漂白力がありますが、フローリングでの使用はおすすめできません。
その理由は以下の通りです。
- 強い塩素成分がワックス層を破壊し、色ムラや剥がれを引き起こす
- 成分の水酸化ナトリウム(強アルカリ性)が木材に残留し、床を劣化させる
- ペットや赤ちゃんへの刺激が強く、安全性にも不安がある
塩素系カビ取り剤は水で流せる浴室向けの製品なので、フローリングでの使用は避けるようにしてください。
2-3. 重曹・酢などナチュラル洗剤を使用する

重曹や酢は「環境にやさしい掃除アイテム」として人気ですが、フローリングのカビ取りには不向きです。
重曹は粉のまま使用すると研磨作用で床を傷つける恐れがあり、また濃い重曹水はワックスを溶かして白濁やベタつきの原因になります。
一方、酢は殺菌力が弱く、場合によってはカビの栄養源になってしまうこともあります。
さらに、酸の作用で木材を傷めるリスクも否定できません。
こうしたナチュラル洗剤は場所によっては有効ですが、フローリングのカビ取りには使用を控え、専用の除去剤を使うことをおすすめします。
カビ汚染度調査・ガス滅菌・カビ取りをご検討の方はこちらからお問い合わせください。
3. 黒カビの見極め方とフローリングの正しいカビ取り方法
黒カビであっても、発生が浅く表面にとどまっている軽度の状態であれば、自力で除去できるケースもあります。
しかし、黒カビは非常に厄介で、すでにフローリングの奥深くまで根を伸ばしている場合は、専門業者でも完全な除去が難しく、リペアやリフォームが必要になることもあります。
無駄な手間や費用をかけないためにも、まずはそのカビが自力で対応できる段階かどうかを見極めることが重要です。
3-1. そのカビ本当に取れる?除去前にできる簡易チェック

フローリングに使用できるカビ取り剤を購入したあとで、「実は取れないカビだった」と気づいてしまっては、時間もお金も無駄になってしまいます。
そうならないためにも、事前に自力で除去可能なカビかどうかをチェックしておくことが大切です。
用意するもの
- 塩素系漂白剤(例:キッチンハイターなど)
- 歯ブラシ
- 雑巾
- マスク
- ゴム手袋
塩素系漂白剤は、一般的なカビ取り剤と同じように漂白効果があります。
これを使って試し塗りをすることで、除去可能かどうかを判断することができます。
作業の際は、マスクやゴム手袋を着用して身体を保護し、必ず換気をしながら行いましょう。
花王 キッチンハイター

出典: Amazon
手順

漂白剤の原液をカビ部分に塗布し、10分ほど放置してみてください。
もし黒カビの色が薄くなっていれば、そのカビはカビ取り剤で除去できる可能性があります。
3-2. フローリングの黒カビを除去するなら「カビ取りマイスターキット」で紹介する方法を試してみてください。
逆に、変化が見られない場合は、すでに深く根を張っている状態と考えられます。
その場合は無理に自力で対応せず、リフォーム業者への相談をおすすめします。
その場合は、4. 個人でのカビ取りができない場合はプロに依頼するを参考にしてください。
なお、作業が終わった後は漂白剤が床に残らないよう、雑巾でしっかりと水拭きして、フローリングをしっかり乾燥させてください。
3-2. フローリングの黒カビを除去するなら「カビ取りマイスターキット」

小さなお子様やペットがいるご家庭では、床に有害な成分が残っていると誤って舐めてしまうリスクがあります。
大人でも、成分が肌に触れたり吸い込んだりすることで体調不良を起こす可能性があるため、フローリングのカビ取りには安全性の高い液剤を使うことがとても重要です。
そこでおすすめなのが、ハーツクリーンが開発した「カビ取りマイスターキット」です。
この製品は、一般的なカビ取り剤に含まれる毒性の強い水酸化ナトリウムを含まず、乾くと塩になる成分を使用しているため、高い安全性があります。
また、実際にカビ取り業者が現場で使っている液剤を家庭用に改良したもので、除菌力も非常に高いのが特長です。
さらに、防カビ剤もセットになっており、除去後の再発防止にも効果があります。
今回はこちらの商品のライトキットを使用してカビ取りする方法を紹介します。
用意するもの
- カビ取りマイスターキット
- スプレーボトル
- 雑巾
- マスク
- ゴム手袋
- ゴーグル
- 長袖の服
カビ取りマイスターキットには除カビ剤、防カビ剤、カップ、ハケなどがセットになっています。
作業中はカビの胞子が舞ったり、カビ取り剤が飛び散ったりする恐れがあるので、マスク、ゴム手袋、ゴーグル、長袖の服で保護してください。
注意事項
- 作業中は必ず換気する
- 他の液剤と混合しない
- 目立たないところで試してから作業を行う
除カビ剤はフローリングの種類によっては色落ちする恐れがあるので、目立たないところで試してからカビ取りするようにしましょう。
鉄に付着すると錆びることがあるため、除カビ剤が付着してしまった時は水拭きしてください。
手順

①除カビ剤を塗布する
キット付属のカップに除カビ剤を注ぎ入れてください。
そしてハケを使って、カビやカビの周辺に除カビ剤を塗布していきます。
②10~30分ほど放置する
液剤が浸透するまで10~30分ほど放置します。
③雑巾で除カビ剤を拭き取る
硬く絞った雑巾で除カビ剤を拭き取り、乾燥させてください。
④防カビ剤を噴霧する
スプレーボトルに防カビ剤を注ぎ入れます。
そして先ほどカビ取りをした箇所に防カビ剤を噴霧してください。
⑤自然乾燥させる
しっかりと乾燥させて終了です。
3-3. フローリングに青カビ・白カビが発生した場合の対処方法

フローリングには青カビや白カビが発生することもあります。
これらは木材の表面にとどまることが多く、自力での除去が比較的しやすいのが特徴です。
ただし、胞子が非常に飛散しやすく、放置すると一気に広がってしまうため、早めの対応が重要です。
自力で除去する場合の対処法
青カビ・白カビにも、先に紹介した「カビ取りマイスターキット」は有効です。
より手軽に対処したい場合は、消毒用エタノール(濃度70%前後)をスプレーして拭き取る方法もおすすめです。
作業の流れは以下の通りです。

また、作業時は以下の点に注意しましょう。
- 火気厳禁(アルコールは引火性あり)
- 必ず換気を行う
- フローリングのワックスが溶ける可能性があるため、目立たない場所で試す
ドーバー パストリーゼ77

出典:Amazon
健栄製薬 消毒用エタノールIP

出典: Amazon
安全性と持続性を求めるなら「銅イオン水」がおすすめ

「エタノールでは刺激が強い」「除去後も抗菌効果を持続させたい」という方には、銅イオン水による対策もおすすめです。
中でも弊社が独自開発した「コパリン(クリーンプロテクション®CU2+)」は以下の特長を持ち、フローリングでの使用にも非常に適しています。
- アルコール以上の除菌力
- 引火性がなく、安全性が高い
- 木材やワックスへの影響が少ない
- 抗菌効果が持続
カビ除去後の仕上げや、日常的な防カビ対策にも活用できます。
再発リスクを抑えたい方には、一歩進んだ選択肢といえるでしょう。
カビ汚染度調査・ガス滅菌・カビ取りをご検討の方はこちらからお問い合わせください。
4. 個人でのカビ取りができない場合はプロに依頼する
黒カビの進行具合によっては、自力での除去が難しいケースがあります。
特に、カビの根が木材の奥深くまで入り込んでいる場合は、市販の除去剤では効果がなく、無理に対応すると状態を悪化させてしまうおそれもあります。
また、発生したのが青カビや白カビであっても、広範囲に広がっている場合は自力での対処が難しく、再発を繰り返す原因になりかねません。
「表面のカビが何度も再発する」「変色が取れない」「床が軋む・浮いている」などの症状が見られたら、早めに専門業者に相談しましょう。
4-1. カビ取り業者に依頼する

カビが広範囲に広がっている場合や、何度除去しても再発を繰り返している場合は、専門のカビ取り業者に依頼するのが最適です。
特にフローリングに発生したカビは、歩行によって胞子が空気中に舞い上がり、まだ発生していない周囲の床や壁にまで広がるリスクがあります。
また、目に見える部分だけを取り除いても、内部に菌が残っていれば再び増殖してしまうため、徹底した除去が必要不可欠です。
当社ハーツクリーンでは、これまでに10,000件以上のカビ調査と、5,000件以上のカビ施工実績があります。
官公庁・病院・上場企業といった、より高い技術が求められる現場でも多数の対応実績があります。
また、海外の大学と共同開発した独自のカビ除去・防カビ液剤を使用しており、3年の再発率はわずか5%以下と、業界でも最高レベルの品質を維持しています。
ご自宅のフローリングだけでなく、職場・店舗・施設などの床に発生したカビ対策にも対応可能です。
カビでお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
4-2. リフォーム業者に依頼する

黒カビがフローリングの奥深くまで浸透してしまっている場合、たとえカビ取り業者でも完全な除去が難しいことがあります。
その場合は、床材のリペア(部分補修)やリフォーム(張り替え)が必要になるケースもあります。
リペアであれば、部分的な修繕で済むため、コストを抑えることが可能です。
ただし、被害が広範囲に及んでいる場合や根太にまで侵食している場合は、全面リフォームが必要になることもあり、費用も数十万円規模になることがあります。
また、フローリング以外にも壁や天井、建材の見えない部分にまでカビが広がっている可能性もあります。
このような場合、床だけをリフォームしても根本的なカビの解決にはならないこともあるため、まずはカビの専門業者に相談するのが安心です。
カビ汚染度調査・ガス滅菌・カビ取りをご検討の方はこちらからお問い合わせください。
5. 黒カビはなぜ生える?フローリングにカビが発生しやすい原因
ここまで、フローリングに黒カビが発生した際の除去方法や対処法について解説してきました。
しかし、カビ対策で本当に重要なのは、「カビを発生させない環境づくり」です。
そのためにはまず、カビがどんな条件で繁殖するのかを理解する必要があります。
まず、カビは以下の4つの条件が揃っている場所に発生します。

このうちどれか1つでも欠ければ、カビの発生を抑えることが可能です。
では、これらの条件がフローリングのまわりでどのように揃ってしまうのか、具体的に見ていきましょう。
5-1. 室内が暖かくて湿度が高い

現代の住宅はエアコンによって、季節を問わず室温20〜30℃に保たれていることが多く、これはまさにカビにとって快適な温度です。
さらに、湿度が60%を超えるとカビは活発に増殖します。
ちなみに、気象庁のデータによると、2024年で相対湿度が60%以下だったのは3か月だけでした。
それだけ日本の気候は、年間を通じて高湿度状態が続いているということです。
また、空気が乾燥しがちな時期でも、加湿器の使用や洗濯物の室内干しによって、室内の湿度が高まっているケースもよくあります。
5-2. 局所的に湿気がこもっている場所がある

部屋全体の湿度がそれほど高くなくても、床の一部にだけ濡れていたり、湿気がこもっていたりすると、そこにカビが発生することがあります。
たとえば以下のようなケースです。
- マットや布団が濡れていて、そのまま敷きっぱなし
- 窓際で結露が床に落ち、湿気がこもる
- 観葉植物の受け皿に溜まった水分が周囲の湿度を上げている
このような「湿気のたまり場」は、フローリングカビの温床になるため、日頃から注意が必要です。
5-3. カビの栄養源となる汚れが蓄積している

カビも生物である以上、繁殖には「栄養」が必要です。
フローリングには以下のような汚れがたまりやすく、カビにとっては恰好の栄養源となります。
- ホコリ
- ダニの死骸
- 人間の皮脂・汗
- 食べカスや飲み物の飛沫 など
掃除を怠っているとこれらが蓄積し、カビの胞子が着地・定着しやすくなるため、定期的な掃除が重要です。
特に湿度も高い時期や場所では、数週間で一気に繁殖するリスクがあります。
カビ汚染度調査・ガス滅菌・カビ取りをご検討の方はこちらからお問い合わせください。
6. 二度とカビを発生させない!フローリングの7つのカビ対策
前章でご紹介したとおり、フローリングは温度・湿度・汚れといったカビの好条件がそろいやすい場所です。
だからこそ、これらの条件がそろわないように環境を整えることが、カビ予防の基本となります。
ここでは、フローリングに黒カビを再発させないための、今日から実践できる7つの具体的な対策をご紹介します。

6-1. 定期的に換気する

窓を閉め切っていると湿気がこもり、室内の湿度が上昇してしまいます。
湿気を逃すために、1日1〜2回は窓を開けて換気する習慣をつけましょう。
また、窓は1か所だけでなく、対角線上に2か所以上開けると効率よく空気が循環します。
カビは空気が滞留しやすい場所に発生しがちなので、換気によって空気の流れをつくることがカビ防止に直結します。
6-2. 除湿する

カビ対策において、湿度の管理は最も重要なポイントです。
特に梅雨時や夏場は湿気がこもりやすく、少し油断するだけでカビが一気に繁殖する原因になります。
湿度が高いと感じたら、除湿機やエアコンの除湿機能を使って、室内の湿度を40〜60%に保つようにしましょう。
湿度が把握できていない場合は、湿度計を設置することで数値の変化が見えるようになり、管理がしやすくなります。
タニタ 温湿度計

出典: Amazon
6-3. こまめに掃除する

カビはホコリや皮脂、ダニの死骸などを栄養源として繁殖します。
特にフローリングは、素足で歩いたりホコリが溜まりやすかったりするため、放っておくとすぐにカビの栄養だらけの状態になってしまいます。
そのため、こまめな掃除で栄養源を断ち、カビの発生を未然に防ぐことが大切です。
また、定期的に掃除をしておけば、カビが発生したとしても早期に気づける可能性が高く、自力で簡単に除去できることもあります。
6-4. 濡れたらすぐに拭き取る

フローリングに水分が残ったままになると、そこからカビが発生する原因になります。
特に黒カビは湿った場所を好むため、水分の放置はカビの発生リスクを一気に高めてしまいます。
キッチンや窓際、結露が出やすい場所などは特に注意が必要です。
また、マットや家具の下など目につきにくい場所は、湿気に気づかず発見が遅れるケースも多くあります。
濡れやすい場所にはできるだけ物を置かないようにし、定期的に移動させて湿気がこもらないようにすることが大切です。
万が一濡れてしまった場合は、できるだけ早く拭き取り、しっかり乾燥させましょう。
6-5. 観葉植物を床に置かない

観葉植物は室内に癒しを与えてくれますが、水分・肥料・土というカビの好物が揃っているため、カビの発生源になりやすい点には注意が必要です。
水やりの際に床に水がこぼれたり、受け皿に溜まった水分が湿気を高めることで、植物の周辺にカビが発生してしまうケースは少なくありません。
対策としては、すのこやプラントスタンドを使って床との接地を避け、通気性を確保することが効果的です。
また、床が濡れてしまった場合はすぐに拭き取り、湿気を残さないようにしましょう。
6-6. 万年床にしない

布団を敷きっぱなしにしていると、就寝中にかいた汗(コップ1〜2杯分)が床にこもり、カビの温床になってしまいます。
特に、吸湿性の低いポリエステル素材の布団は汗を吸収しきれず、床に湿気が溜まりやすくなります。
カビのリスクを減らすためには、毎朝布団を畳む習慣をつけることが理想的です。
難しい場合は、ベッドに変える・すのこマットを敷くなど、布団と床の間に通気性を確保する工夫を取り入れましょう。
アイリスプラザ すのこマット

出典: Amazon
6-7. 家具選びや配置も大事

「気づいたら大型家具の裏にカビがびっしり…」というのは、実はよくあるケースです。
特に通気性が悪く、長期間動かしていない家具の裏側や下部は、湿気がこもりやすくカビが発生しやすいため要注意です。
家具を新しく選ぶ際は、脚付きのベッドやソファなど、床との間に空間があるものを選ぶと湿気がたまりにくくなります。
また、湿気がこもりやすい窓際には家具を極力置かないことも大切です。
やむを得ず置く場合は、移動しやすい小型家具やキャスター付き家具にすることで、定期的な点検・通気がしやすくなり安心です。
カビ汚染度調査・ガス滅菌・カビ取りをご検討の方はこちらからお問い合わせください。
7. まとめ
今回は、フローリングに発生した黒カビへの正しい対処法と、再発を防ぐための具体的な対策について解説しました。
黒カビは木材の奥深くまで根を伸ばす性質があるため、表面を拭いただけでは除去しきれず、再発を繰り返す非常に厄介な存在です。
誤った方法で対処すると、かえって被害を拡大させてしまうため、正しい手順と安全な除去剤を使った対応が欠かせません。
軽度であれば、カビ取りマイスターキットのようなフローリング対応のカビ取り剤で自力での除去も可能です。
その場合は以下の手順で行いましょう。

しかし、カビが広範囲に広がっている・再発している・床が変色・変形しているといった場合は、早めに専門のカビ取り業者に相談することをおススメします。
ハーツクリーンでは、カビの調査・除去実績が豊富にあり、住宅から商業施設まで多様な現場に対応しています。
3年の再発率はわずか5%以下という業界最高レベルの品質を提供していますので、フローリングの黒カビでお困りの方はぜひ一度ご相談ください。
また、黒カビがすでに床材の内部や下地まで侵食している場合は、カビ取りだけでは対応できず、リペアやリフォームが必要になることもあります。
その場合は、専門業者と相談しながら、被害の状況に応じた対応を検討することが大切です。
いずれにしても、黒カビを発生させないための予防策こそが最も効果的な対処法です。
以下のカビ対策を日々の生活に取り入れて、黒カビの原因となる湿気と栄養をため込まない環境づくりを意識していきましょう。

この記事が、フローリングの黒カビに悩む方の問題解決に少しでも役立つことを願っています。